ISO認証

JIA-QAセンターは、日本ガス機器検査協会(JIA)のISOマネジメントシステム認証部門として1993年に設立されました。お客様とのコミュニケーションをより一層充実させてお客様のニーズの把握に努め、ニーズにあった認証プログラムを確立させ、「満足から感動に繋がる認証サービスの提供」を目指します。

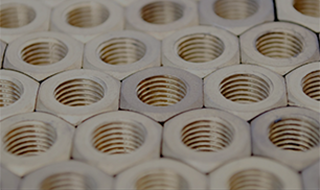
ISO9001
ISO9001
品質マネジメントシステムの要求事項を定めており、顧客重視、プロセスアプローチ、文書化などにより業務の改善に寄与します。

ISO14001
ISO14001
環境マネジメントシステムの国際規格です。環境汚染予防を促進するとともに、コスト削減などで経営環境の改善に貢献します。

ISO22000
ISO22000
食品安全に関するマネジメントシステム規格です。 安全な食品を提供するためにフードチェーンの組織に対するマネジメントシステムの構築に貢献します。

FSSC22000
FSSC22000
細菌やウィルスによる食中毒をはじめ、昨今では食品への異物混入、表示偽装等の脅威から色の安全を守ります。

JFS-C
JFS-C
腐敗しやすい製品の加工、化学製品の製造などが対象の日本発の食品安全マネジメントシステムの認証スキームです。

JIA-GMP
JIA-GMP
JIA-QAセンターは、JIA食品施設の衛生及び品質基準に基づき食品衛生システム認証を行っています。

ISO45001
ISO45001
労働災害リスクを最小限に抑えるとともに、将来のリスクを予想し回避することを目的としたマネジメントシステム規格です。

IATF 16949
IATF 16949
自動車組立メーカーを最終顧客としたサプライチェーンの組織の品質マネジメントシステムの構築に貢献します。

ISOセミナー
ISOセミナー
セミナーのご案内、開催日程など、ご確認いただけます。

審査体制
審査体制
価値ある審査のための3つのスタンスをご紹介します。

他機関からの切替え審査
他機関からの切替え審査
JIA-QAセンター以外で審査登録の移転をご希望のある場合にはぜひ当センターにご相談ください。

統合審査案内
統合審査案内
同時に、二つ以上のマネジメントシステム規格の要求事項に関して審査する統合審査をご提供しています。

登録組織向けサポート
登録組織向けサポート
セミナーのご案内など、登録組織に役立つ情報をご案内します。

登録事業者検索
登録事業者検索
ISO 9001、ISO 14001、ISO 22000、FSSC 22000、ISO 45001の審査登録組織について、検索条件を入力して登録事業者を検索することができます。

JIA-QAセンター概要
JIA-QAセンター概要
公正且つ厳格な審査で企業の継続的改善をお手伝いします。

認証のプロセス
認証のプロセス
認証の授与、拒否、維持、更新、一時停止、復帰、取消し、並びに範囲の拡大及び縮小のプロセスについてご案内します。

異議申立て、苦情の取扱いについて
異議申立て、苦情の取扱いについて
JIA-QAセンターの審査登録業務に関する異議申立て、苦情を以下の通り受け付けについてご案内します。

お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用ください。





 ガス機器設置に係る初級者向け実技講習
ガス機器設置に係る初級者向け実技講習


